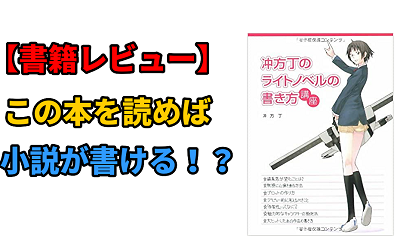エスジェイ(@crisisnoeln)です。
ぼくは小説を書こうとしているのだがなかなか進まないでいる。というか1文字も書けていない。
漠然と書きたい話はあるのだが、いざ書こうとしても細かい設定とか云々いろいろと何をどうすれば分からない…。
これは勉強したくても勉強の仕方が分からないという理屈に似ている。英語の勉強はしたいけど、まず何をすれば良いのか分からない。みたいなものだ。
そこで奥の手として小説の書き方的な本を読むようにしてた。
最初からそうしなかった理由は、森博嗣のエッセイ本の影響が少なからずあったからだ。
彼いわく、小説の書き方本やら小説の練習なんて邪道らしい..。
理屈とかよくわからんが、直感的になんか良いこと言っている気がしたのでしばらく自力でやろうと試みたが、結局なにも進まなかったのでやっぱり指南書を読むことにした。
冲方丁のライトノベルの書き方講座

タイトル通り冲方丁氏によるライトノベルの書き方指南書。
まさにドンピシャなタイトルだったので読んでみることにした。
ぼくは冲方丁という作家は知りませんでしたが、そこそこ有名な方のようです。
余談ですが、ファフナーはパチンコの攻略法が超有名なので「蒼穹のファフナー」だけは彼の作品で唯一知ってました。(読んではいません)
本書の作者の作品は知らなかったので先入観なく読めました。
本書で気になった部分を抜粋していきます。
種書き、骨書き、筋書き~
まずは「種書き」という作業をしていくようです。
種書きとは、これから書こうとしていることを漠然と文字起こししていく作業とのこと。
ちなみに種書きという言葉自体は沖方氏の造語のようです。
「少女、戦闘、葛藤」のようにひたすらイメージする単語を上げていきます。
「戦闘以外の戦い、少女の乗り越え、人間への価値」など漠然とテーマや趣旨を上げたりもするようです。
ある程度、種書きが終わると次に『骨書き』という作業工程に移ります。
骨書きは一般的に企画書のようなものだといいます。
ここで登場人物の性格であったり、世界観、あらすじなど固めていきます。
『種書き→骨書き→筋書き→肉書き、骨書き』と作業工程を進めていきます。
だいたいの作業内容は言葉通りの意味合いになっています。種書きで種を撒き、骨書きで核となる骨を作る。肉書き、皮書きで細部を整えていく仕上げ作業をする。
本書のこの工程説明ではかなり具体的な話に触れているので非常に参考になります。
作品を完成させるためには・・
完璧主義よりも完了主義というマーク・ザッカーバーグの格言もありますが、それでも漫画や小説は完成させれない人は多いのも事実です。
作品を完成させるために必要なことに以下の3つを上げている。
1.締め切り
2.優先順位
3.下書き
〆切を作ることで期間を決める。自分はどれくらいのものをどれくらいで作れるのかを知る必要がある。
優先順位を作ることで書きたいものを明確にできる。どんなささいなアイデアでも優先順位をつける。
下書きはプロットや梗概など。優先順位を確認しながらしっかり作る。
この3つをしっかりと下準備しておけば作品はだいたい最後までしっかりと書けるといいます。
本書の感想まとめ
思っていたよりも実践的な内容で参考になりました。
前にレビューした書き方系の本は漠然とした内容で「小説とは何か?」という感じで具体的な書き方とかにはいっさい触れていませんでした。
この本を読んで「指南書なんてまあこんなものだろうな」という印象があったので、本書を読んでちゃんと書いてくれるのかという面でも驚きはあった。
あまり売れる小説の書き方とかをやると、ノウハウ流出みたいな感じでマズイ感じもするが、本書では小説界に今必要なのは1000人の中堅作家、1万人の新人作家、そして100万人の同人作家なのだという。
『読む楽しさから書く楽しさへ』という謳い文句も提唱しており、基本的には小説人口が増えることに前向きで小説人口(特に書き手)を増やしたいのだと意図がうかがえる。
小説を書く気がない人でも「なるほどな」と関心できる話も多いので、仕組みを知るという意味でも楽しめるのでおすすめしたい1冊である。
「ライトノベルの書き方」とタイトルにあるが、別にライトノベルに限った話ではないので、ラノベを読まない人でも楽しめるだろう。
ぼくもあまりラノベは読まないし、ラノベを書こうとは思はないが、凄い参考にはなった。なにか今なら書ける気がする。とりあえず種書きから実践していこうと思う。