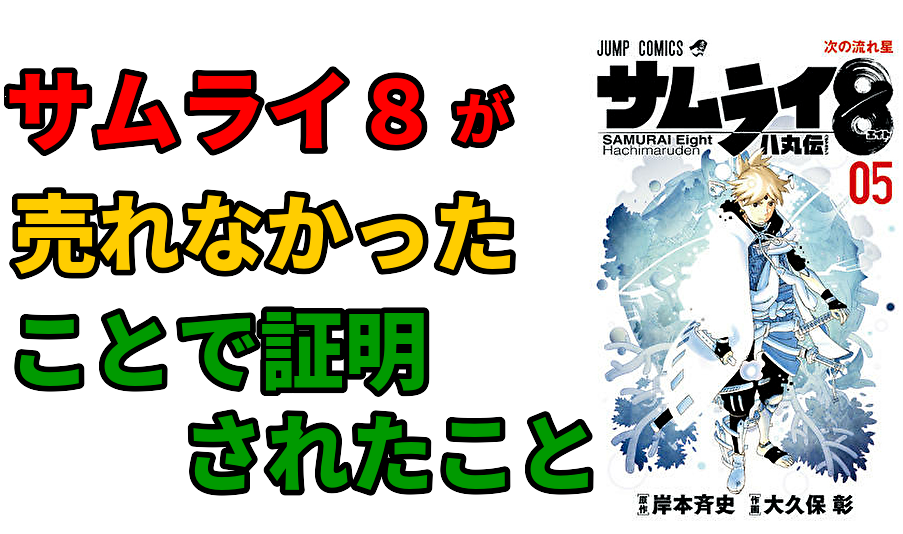NARUTOの岸本斉史氏原作でNARUTOの元アシ大久保氏が作画を担当し話題となった漫画サムライ8。
この漫画はジャンプで連載開始とともに、様々な媒体で広告が打たれかなり話題なりました。
個人的にもかなり期待していたし、岸本斉史の原作はNARUTOの続編であるBORUTOもありますが、サムライ8は完全にナルトとは別世界の作品ということでの期待値も高かったこともあります。
しかしながら、周囲の期待や膨大の広告費も虚しく結果的にサムライ8は人気が取れず連載開始1年ほどで打ち切りでなりました。
ぼくも1巻を読みましたが、設定の難解さや魅力の薄い登場人物などもあり、あまり面白いとは思えませんでした。
ここでは内容云々は置いておいて、サムライ8が売れなかったことで証明された事実について少し考えていきます。
サムライ8の売上げ
まずはサムライ8が実際にどれくらい売れたのかのデータです。
数値はネットの噂レベルなのでどこまで正確かは定かではないですが、発行部数とかは調べる方法も確立しているのでネットで出回る情報レベルでもわりと正確な数値だと思います。
本の発行部数を調べる方法はこちら
[kanren postid=”2098″]
サムライ8は1~2巻が同時発売で約4万部。
3巻が4万部弱、4巻は1万部弱の売上げだったようです。
この数字だけ見ると、今どきの漫画は1万部初版で売れればそれなりなので、そこまで悪くないように思えますが、サムライ8は同時期の人気作品であった鬼滅の刃と同じくらい初版部数が刷られたという噂があります。
鬼滅の刃は最終巻の初版で300万部という記録を出しましたが、勢いに乗りはじめた鬼滅の刃と同数くらい(当時の初版だと数十万部ほど)サムライ8は初版が刷られたという話もあります。(この辺の事実は不明)
このあたりが、広告費を多大にかけているという話に繋がってきます。
鬼滅の刃でも何でも初版の発行部数は通常売れると予測される部数の2倍くらいが出版の目安です。
予測で1万部は売れると思われるなら、最初に2万部くらいを刷るというのが一般的です。
常に刷った分の50%は最低でも売れていく計算で刷られ、70%を超えたあたりで増刷するというのが通常の流れになります。
サムライ8は、おそらく初版で数十万部は用意されており、数万部しか売れていないので数十万部も売れ残ったということになります..。
さらには作品を宣伝するための広告費も相当かけています。様々な媒体で広告を出していました。
事実は分かりませんが、サムライ8は少年ジャンプの歴史上で最も赤字になった漫画ともいわれています。単純計算でも数億円の赤字にはなります。
なぜ売上げの憶測を見誤るのか?
ここで問題になるのは、売れなかったこと以上に「売れ行きの予測を大きく見誤った」ことです。
そもそも赤字は売上げ予測が正確にできていれば起きようがありません。
5000部しか売れてない漫画でも1万部しか刷ってなければ大きな損害はありません。
ではなぜ、売れない作品にここまで大きく宣伝費をかけたかといえば、当然ですが『売れると思っていたから』だといえます。
売れると予測していた部数と実際に売れた部数が想像以上に大きかったという点。
これは大手出版社でも売上げの予測を確実にすることは不可能だと証明したことにも繋がります。
もう1点『面白くない作品に広告費をかけても売れない』ということも証明されました。これも大きいです。
必ずしも「面白い=売れる」ではない
当たり前ですが、世に出る作品はすべて売り物なので、売れる前提で作ります。
売るためには作品の面白さが必要ですが、今の時代は面白いだけでは売れないと言われています。
まずは作品を手に取ってもらうための宣伝が必要です。
何でも広告なしで0から売るというのは不可能なので広告費は少なからずかかります。
「面白さ+宣伝」これが売れるためには必須条件になります。
宣伝するにはお金がかかるので、最初からある程度売れるだろう思える作品でないとなかなか広告費をかけることはできません。
つまり最初から膨大な宣伝費をかけるということは、製作者側はかなりの自信がある作品ともいえるのです。つまり最初から面白いと思われている作品が対象になります。
通常の場合は、5000部、1万部と少ない部数で試して、何かをきっかけにバズったりして一気に人気に火がつくことはあります。
何の実績のない作品がいきなり初版で数十万部を刷って広告費をドーンと出して宣伝するなんてことはありえないわけです。
このあり得ないことをして見事に大ゴケしたのがサムライ8でした..。
まとめ
売れている作品は必ず面白い。
しかし売れていない作品でも面白いものはたくさんある。
では逆に、面白くはないがゴリ押しで売れている作品はあるのか?
これに関しては思っている以上に証明することが難しい。
わざわざ面白くない作品に多大な費用を投資するバカはいないからである。
もう1つは『面白い』の定義が曖昧であるというのもある。
サムライ8は岸本斉史がNARUTOで学んだノウハウをすべて投入した自信作だったという。
ひょっとすると、ぼくらが気がついていないだけでサムライ8は面白いのかもしれないし、潜在能力はあったのかもしれない..。
少なからず出版社だってアホじゃないので「売れる見込み=面白さ」はあると思っていたはずだ。
しかしながら、結果だけを見るとサムライ8は「面白くない漫画に膨大な広告費をかけて大ゴケした」というのは紛れもない事実だ。
面白いと思われない作品はどれだけ売り込んでもゴリ押しで売ることはできない。これが証明されたのだ。
メガヒットを生み出す敏腕編集者みたいな者に注目が集まりがちだが、実はメガヒットさせる法則性なんてものはあってないようなものだ。
そんなものが意図的に生み出すことができるのなら全新人漫画家が吾峠呼世晴になれる。
サムライ8はメガヒットというのは狙って起こせるものではないという事実も証明してくれた。
失敗は成功のもとともいうが、ヒット作品を生む上ではサムライ8のような大失敗のほうが実は学べることは大きのではないだろうか。
もちろん「なぜサムライ8は大ゴケしたのか?」なんてことを公式で岸本斉史や編集担当者にインタビューできるわけもないので黒歴史として今後も表舞台で触れられることはないだろう..。