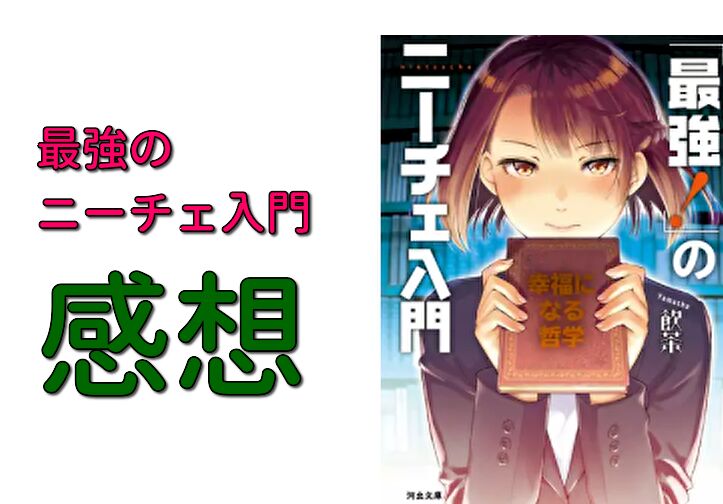飲茶氏のニーチェ入門書を読んだ。
非常にわかりやすかったので簡単に気になる部分を抜粋紹介していく。
最強のニーチェ入門書
哲学とは何か?
哲学は大きく分けると2種類ある。
「本質哲学」と「実存哲学」である。
本書では「白哲学(本質)」と「黒哲学(実存)」と説明している。
色のイメージ通りで、白が王道、黒は邪道の哲学ともいえる。
本質哲学は、愛とか正義という「モノを超えた概念」の本質や意味を考えるようなことで、我々がイメージするような哲学といえる。
一方で実存とは「現実存在」の略語であり、本質や意味を否定し、現実の存在に目を向けた哲学としている。
ニーチェの哲学
ニーチェは、宗教、仕事、恋愛など人の支えとなる絶対的なものはいつか崩壊すると主張している。
「痩せたい、30歳までには結婚して子供産んで、幸せの家庭を築きたい~。」など、そんなものはすべて現代社会が作り出しただけの「背後世界」であり、現実ではなく本来は存在していないものである..。
にも関わらず、それが達成できたとかできなかったなどで勝手に不幸になったりする。
これはおかしいだろうと。
背後世界の概念が理解できてくると、宗教や仕事、恋愛などに意味がないことに気がつくが、そうなると今度はニヒリズムに陥りやがては末人になるという。
ニヒリズムとは「虚無主義」のことで、人間の存在に意義や本質的な価値などはないと思うこと。
末人とは、なんの目標もなくトラブルを避け、ひたすら時間をつぶし続けるだけの人のこと。
人生に意味がないと気がつくと人々は末人となり、やがて社会は末人で溢れかえるのだと..。
我々が生きる日本の現代社会では、まさにそういう人(末人)が増えており、ニーチェは当時(1800年代半ば頃)からこれを予言していたという。
結論からいうと、ニヒリズムを回避するためには「今この瞬間を肯定して生きる」しかないという。
感想
さすが入門書だけあって分かりやすい。
とはいえ内容は哲学の小難しい話というか、屁理屈じみた内容も多いため、興味のない人からすると「はぁ…」って感じにもなるだろう。
哲学の入門書を読んだからといってとくに何が変わるわけではないが、たまにはこういう本も読んでみるのも良いものだ。
個人的には、社会の作り出した価値観を疑問に思うみたいなことは幼いころから当たり前にやっていたことなので、愚問ではあったのだが、ニヒリズムになったり末人になったりする節は確かにあった。
そしてその対処法、そこに至るまでの永劫回避という考え方だったり、なるほどと関心できたところも多々あった。
余談だが、哲学は入門書のほうが専門誌よりも圧倒的に売れている(絶対数が多い)特別なジャンルでもある。
例えば、イラストの描き方という入門書は数多く存在しているが、
実際に描かれるイラスト数より入門書のほうが多いなんてことはありえないわけで..。
しかし哲学というジャンルは、実際に「哲学」を用いる以上に圧倒的に入門書そのものの需要が多いという。
仮に、『同人誌の数より同人誌を作るための方法を説明した書籍のほうが多い』といわたら、実に奇妙な話だと感じるだろう。
しかし哲学というジャンルは実際にそういう現象が起こっている。
哲学を用いる人よりも、哲学の入門書を読みたいという人のほうが圧倒的に多いのである。
それほどに哲学というジャンルの難解さ、何よりも特別に役に立つようなことではないということでもある。
それでも哲学を学ぶと、少しは生きやすくなったりすることもあるだろう。
総括
なんとなしに表紙絵が目に止まって読んでみたが最後までスラスラと読めた。
あまり気難しく考えだすと内容が入ってこないというかキリがない気もするので気楽に読んだほうが良いだろう。
表紙絵の女子はただ客引きのためのラノベ風表紙かと思ったが、しっかりと本編にも登場する。
本書は著者の飲茶氏が先生となり表紙絵の女の子が質問していく形式で展開していく。
自己啓発本にありがちなドジでおバカな女の子との掛け合いも本書の魅力のひとつともいえる。
いかにも生徒と先生という風に演出しているが、おそらく実際に女の子を使ってインタビューさせているわけではなく、あくまでもおバカ女子を飲茶氏が脳内で作り自作自演でやっているのだろう…。
それも考慮してもう一度読み直すと寒いやりとりも笑けてくるから不思議なものだ。
本書を読んでみて、また別の哲学者の解説本か、あるいは白哲学のほうの解説本も読んでみたくなった。
クオリティ高いので別の哲学者版も出そうな気がする。