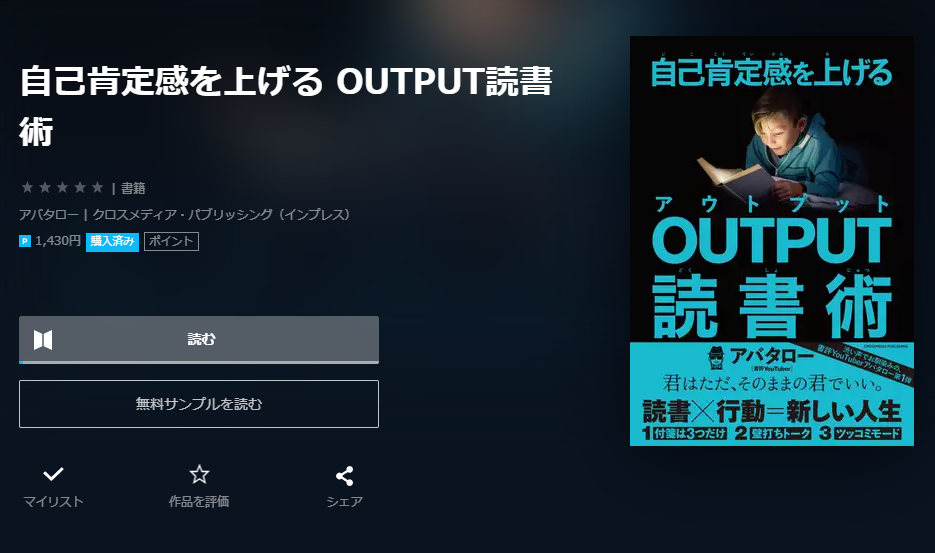エスジェイ(@crisisnoeln)です。
アバタローさん著の「自己肯定感を上げるアウトプット読書術」を読破したので感想を書いていきます。
アバタローさんについて
アバタローさんはユーチューブで書評をしているユーチューバーでもあります。
私は本のタイトルで本を買って積ん読中だった時に、たまたま関連動画で出てきたユーチューブで彼の存在を知りました。
ユーチューブの告知で本の存在を知り、なんか見たことあるなと思いリストを見ると「お、この本ワシ、持ってんじゃん!」となり、一気に読んだ次第です。
動画はかなり質の高い読書レビュー動画なのでオススメです。
過去動画の中に1冊くらいは気になる本があると思います。
アウトプット読書術の感想

本を読む理由
本書では本を読む理由を主に3つ上げています。
1.自分のパフォーマンス向上
2.人生のリスクの最小化
3.長い人生を楽しむため
ただ何となく面白そうだからとか、役に立ちそうだからと漠然と本を読む場合が多いですが、本を読む理由を明確化したほうが良いといいます。
また読書の基本3原則として
1.すべて読まなくてもOK
2.多く読めば良いわけではない
3.速く読めれば良いわけではない
という3つを上げており、このあたりの基本的な読書との向き合い方の項目も説得力がありました。
インプットは食事、アウトプットは筋トレ
なかなかありそうでなかったキャッチーな表現で妙に納得してしまいました。
インプットは食事なので、食べないと飢えてしまいます。
脳に影響を与えるイメージでしょうか。
対してアウトプットは筋トレだといいます。
食べてばかりだと太るばかりで体にも良くないので、インプット(食事)したものはちゃんとアウトプット(筋トレ)して筋力つけましょうね。ということです。
岡田斗司夫氏は読書をなぜするのか?
について脳の筋トレみたいなものだと言ってて、当時それを聞いた私は妙に納得した記憶がありますが、正確には『読書は食事でアウトプットが筋トレ』というアバタロー氏の考えの方が腑に落ちますね。
アウトプットの基本
本書はタイトルにもある通り「アウトプット」を前提とした読書術の本です。
アウトプットのやり方に関しては、かなり細かく解説されています。
その中でも個人的に良かったポイントをいくつか厳選し紹介します。
1.アウトプットができない場合の対処法
本を読んで感想を書こうとしても、何を書けば良いのか、何も思いつかない・・。なんて経験ありますよね。
私もブログで本以外にもゲームや映画の感想を書いていますが、すぐに思いつくものもあれば、なかなか感想が出てこない作品も結構あります。
なので、実は私がブログで感想を書けている作品は、実際に見た作品の1/3程度だったりします。
なぜアウトプットできない作品があるのか?
自分でもいまいち分からなかったのですが、本書ではそのヒントが書かれていました。
そもそもアウトプットできない場合というのは、内容が理解できていない場合が多いわけです。
著者が言いたい主張であったり、本のポイントにあたる部分の理解が浅いわけです。
もっといえば、そもそもその本の内容に興味がない場合は理解以前に書く気力も失せるわけです。
そのあたりは選書の部分で詳しく触れられていますが、読む本は広げすぎずに厳選するのを推奨しています。
まずは読む以前の段階で興味があるか、目的意識があるのか?このあたりが前提としてだいじになるとうのは意外と盲点でした。
興味があって、しっかりと読んだつもりでもアウトプットできない場合もあると思います。
その場合は、徹底的に相手の話を聞くモードにシフトすることがだいじだといいます。
基本的な話ですが、自分の納得ではなく、著者の意見にしっかりと耳を傾けるというのは確かに内容を把握する上では重要なことです。
ペンと付箋の使い分け
個人的になるほどと関心したのが、ペンと付箋の使い分け方です。
ペンとか付箋とかって、いまいち使い方もわからないし、とりあえず重要っぽいところにパーってテキトーにやりがちですが、これに意味を持たせる方法を紹介しています。
ペンは著者の主張で重要だと思う場所にする。
付箋は自分にとって重要だと思う場所にする。
このやり方は個人的には目からウロコでした。
さらに、付箋のはりすぎ防止として1つの本に対して付箋は3つまでと決めるとか、章ごとに1ヶ所付箋を入れて、最後に厳選し3つまで絞るという具体的な方法も紹介してくれています。
本選びの基本
選書の3原則をバフェットの投資理念に基づき3つ紹介しています。
1.自分でも理解できる内容の本を選ぶ
2.信頼できる根拠がある本を選ぶ
3.長期的に価値の下がりにくい本を選ぶ
まずは自分でも理解できる内容でないとダメなので、分からないジャンルなら入門書など簡単なものを推奨しています。
さらに、売れてるとか、人気とか、有名の著者だとか、何かしら根拠のある本から選ぶのもポイントです。
最後に、長期的に価値のある本を選ぶということです。極端な話、1年後には使えないネタの本を読んでもあまり意味がありません。
これはショーペンハウアーの「読書について」という本の中でも書かれていますが、迷ったらギリシアの古典を読むのがオススメのようです。
古代ギリシアにハズレなし!とのこと。
他にも、基本的に古典はハズレがないので、シェイクスピアとか孫子とか、プラトンとか偉人の本は良いぞと、迷ったときの選書術として推奨されています。
まとめ

読みながらメモしていたヶ所を紹介してるだけでも結構な量になりました。
総評すると、初歩的な内容ではあると思いますが、それでもかなり参考になる部分もありました。
基本的に普段あまり読書をしない人向けに書かれているような内容ですが、結構読書をしている私でも参考になる部分は多かったです。
普段いかに漠然と読書をしているのか痛感させられました。
アウトプットの方法として、本書ではアウトプット読書会を推奨していますが、このあたりは若干のビジネス臭を感じてしまいました。
あと「自己肯定感を上げる」という本書のタイトルのキーワードですが、おそらくこれは編集がキャッチーなワードとして使いたかったんだと思います。
自己肯定感の高さだけが取り柄の私が読んでも普通に楽しめましたし、自己肯定感は本の内容と正直あまり関係ないように思います。
本書で自分が一番刺さったポイントは、アウトプットできないのは選書の段階で間違えているということと、著者の意見を組み取ろうとしていないという2点ですね。
私の場合、本は結構読んでますが、選書がかなりテキトーで漠然とテーマを持たずに読んでいましたし、著者の主張よりも自分の納得に重点を置きすぎていたので、著者がどんな人物でどういう生い立ちの元、どういう思考に至りこの本を書いているのか?というところまでは考えたこともありませんでした。
自分にとって納得できない内容だと、「はい、乙。クソ本やな。次~」みたいな感じで、あくまで自分軸になっていた感じですね。
著者の意見を組み取ろうとする姿勢がないと、そもそも読書しても自分の良い情報しか吸収しないわけなので、だったらネットで自分の都合の良いネタだけ収集してれば良いわけですからね。
もっと著者を重んじるというのを1つ自分の中の読書テーマとして今後は取り入れていこうと思いました。
これは読書だけでなく、映画やゲームでも同じことがいえると思います。
監督の意図、クリエイターの思想など、自分の主観だけで捉えない観点は絶対に重要ですね。
自分に足りない部分がハッキリと見えて非常に勉強になりました。
かなりの良書でした^^